 |
 |
���z�i���ȕ��S���x�z�j�Ƃ́H |
 |
 |
 |
 |
| �敪 |
���ȕ��S���x�z |
| |
�W����V���z |
| �A | 83���~�ȏ� |
252,600�~�{�i��Ô�|842,000�~�j×1�� |
| �C | 53���`79���~ |
167,400�~�{�i��Ô�|558,000�~�j×1�� |
| �E | 28���`50���~ |
80,100�~�{�i��Ô�|267,000�~�j×1�� |
| �G | 26���~�ȉ� |
57,600�~ |
| �I | �Ꮚ������ |
35,400�~ |
|
���s�������ł̔�ېŎ҂ł����ی��҂Ɣ�}�{�ҁA�܂��͒Ꮚ���҂̓K�p���邱�Ƃɂ�萶���ی��K�v�Ƃ��Ȃ���ی��҂Ɣ�}�{��
���u�敪�A�v�u�敪�C�v�ɊY������ꍇ�́A�s�������ł���ېœ��ł����Ă��u�敪�A�v�u�敪�C�v�̊Y���ƂȂ�܂��B
���Ꮚ���҂̋敪�K�p����ɂ́A�}�C�i�ی��̗��p�ł����Ă��A�u���N�ی����x�z�K�p�E�W�����S�z���z�F��\�����v�̎��O�\�����K�v�ƂȂ�܂��B
���z�×{��̎Z���1�����Ƃɍs���܂��B
��1���Ƃ͐f�Õ�V����1�����w���܂��B�f�Õ�V�����́A�e��Ë@�֓�������1�l�ɂ��A1�������Ɓi������Ë@�ւł���ȓ��@�A��ȊO���A���ȓ��@�A���ȊO���͕ʈ����j�ɍ쐬���܂��B�@�O�����̏ꍇ�́A��ǂƏ���Ⳍ�t���̈�Ë@�ււ������������������ł���Ε�����1���ƂȂ�܂��B
|
 |
 |
|
 |
| �� �a�@�����ł̎x���������ȕ��S���x�z�܂łɂ������Ƃ� |
 |
| �@�}�C�i�ی��𗘗p����
��Ë@�֓������̃J�[�h���[�_�[�Ń}�C�i�ی���ǂݍ��ނƁA���x�z����ӕs�v�Œ���܂��̂ŁA��Ë@�֑����I�����C���Ŏ��ȕ��S���x�z���m�F���邱�Ƃ��ł��܂��B�]���A���ł��\���E���s����Ă����u���x�z�K�p�F��v�͕s�v�ƂȂ�܂��B
����ی��҂���ېŎ҂̂��ߋ敪�I�̓K�p�������ꍇ�͇A��
�A���x�z�K�p�F��𗘗p����
�}�C�i�ی��������p�ɂȂ�Ȃ��ꍇ�A���O�Ɍ��N�ی��g�����ĂɁu���x�z�K�p�F��،�t�\�����v������o���������B���\�����甭���܂ł͒ʏ�1�T�Ԓ��x�ł����A�X������ɂ��x���ꍇ���������܂��̂ŗ]�T�������Ă��\�����������B
�Ȃ��A��ی��҂���ېŎ҂̂��ߋ敪�I�̓K�p�������ꍇ�́A�Z���Ŕ�ېŏؖ�����Y�t���������B�K�p���ɂ��K�v�ȔN�x���قȂ�܂��̂Ŏ��O�Ɍ��N�ی��g���܂ł��₢���킹���������B |
| |
| |
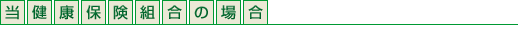 |
| �@���g���ł͗×{�̋��t�i�Ƒ��×{��j�A���z�×{��i�Ƒ����z�×{��j���x�������ꍇ�ɁA�Ǝ��̋��t�i�t�����t�j���s���Ă���A��ی��҂���є�}�{�҂̍ŏI�I�Ȏ��ȕ��S�z�́A1��������20,000�~�i+�[���j�܂łƂȂ��Ă��܂��B���킵���͂���������Q�Ƃ��������B >> �u����������Ô�̂R���𑋌��ŕ��S���܂��v |
��1���Ƃ͐f�Õ�V����1�����w���܂��B�f�Õ�V�����́A�e��Ë@�֓�������1�l�ɂ��A1�������Ɓi������Ë@�ւł���ȓ��@�A��ȊO���A���ȓ��@�A���ȊO���͕ʈ����j�ɍ쐬���܂��B�@�O�����̏ꍇ�́A��ǂƏ���Ⳍ�t���̈�Ë@�ււ������������������ł���Ε�����1���ƂȂ�܂��B
| �� ���z�×{��̕��S�y���[�u |
 |
 |
| �i1�j���э��Z������ |
 |
�@���ꌎ�A���ꐢ�ѓ��ŁA���ȕ��S�z��21,000�~�i�Ꮚ���҂����z�j�ȏ�̂��̂�2���ȏ゠��ꍇ�́A���э��Z�������ȕ��S���x�z�������Ƃ��܂��B
|
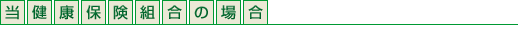 |
| �@���g���ł͍��Z���z�×{��x�������ꍇ�ɁA�Ǝ��̋��t�i�t�����t�j���s���Ă���A��ی��҂���є�}�{�҂̍ŏI�I�Ȏ��ȕ��S�z�́A1��������20,000�~�i+�[���j�܂łƂȂ��Ă��܂��B |
| 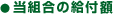
�@���Z���z�×{��i�{�l�E�Ƒ��j���x�������ꍇ�ɁA���̕��S�z�̍��v�z�i���Z���z�×{���ѓ��@���H���×{�ɂ�����W�����S�z�A���@�������×{�ɂ�����W�����S�z�͏����j����1��������20,000�~���T�������z�i100�~�����͐�̂āj������A�x������܂��i�Z�o�z��500�~�����̏ꍇ�͕s�x���j�B������u���Z���z�×{��t�����v�Ƃ����܂��B
|
��1���Ƃ͐f�Õ�V����1�����w���܂��B�f�Õ�V�����́A�e��Ë@�֓�������1�l�ɂ��A1�������Ɓi������Ë@�ւł���ȓ��@�A��ȊO���A���ȓ��@�A���ȊO���͕ʈ����j�ɍ쐬���܂��B�@�O�����̏ꍇ�́A��ǂƏ���Ⳍ�t���̈�Ë@�ււ������������������ł���Ε�����1���ƂȂ�܂��B
 |
| �i�Q�j�����Y���̏ꍇ�̓��� |
 |
|
�@1�N�i����12�����j�̊Ԃɓ��ꐢ�т�3�����ȏ㍂�z�×{��ɊY�������ꍇ�ɂ́A4�����ڂ���͉��\�̋��z�������Ƃ��܂��B
|
| �敪 |
���ȕ��S���x�z |
| |
�W����V���z |
| �A | 83���~�ȏ� |
140,100�~ |
| �C | 53���`79���~ |
93,000�~ |
| �E | 28���`50���~ |
44,400�~ |
| �G | 26���~�ȉ� |
44,400�~ |
| �I | �Ꮚ������ |
24,600�~ |
|
���s�������ł̔�ېŎ҂ł����ی��҂Ɣ�}�{�ҁA�܂��͒Ꮚ���҂̓K�p���邱�Ƃɂ�萶���ی��K�v�Ƃ��Ȃ���ی��҂Ɣ�}�{��
 |
| �i�R�j���莾�a�̏ꍇ�̓��� |
 |
�@���F�a�A�R�E�C���X�܂𓊗^���Ă����V���Ɖu�s�S�nj�Q����ѐl�H���͂�K�v�Ƃ��閝���t�������̒������҂́A���莾�a�̔F�����ƁA��Ë@�ււ̎x������1����10,000�~�ōς݂܂��B
�@�������A�l�H���͂�K�v�Ƃ��銳�҂�70�Ζ������W����V���z53���~�ȏ�ɊY������ꍇ�́A���ȕ��S��1����20,000�~�ɂȂ�܂��B
|
75�ɂȂ�����ی��҂̉Ƒ��̎��ȕ��S���x�z�̓���
�@��ی��҂�75�ɂȂ��Č������҈�Ð��x�̔�ی��҂ƂȂ������Ƃɂ���Ĕ�}�{�҂łȂ��Ȃ���70�Ζ����̐l�ɂ��ẮA���̌��i��ی��҂�75�̒a���������̌��̏����̏ꍇ�͏����j�̎��ȕ��S���x�z������Ƃ��ĂQ���̂P�̊z�ƂȂ�܂��i���i�r����ɉ������鍑�����N�ی����̎��ȕ��S���x�z���Q���̂P�̊z�ƂȂ�܂��j�B
�� 70�Έȏ�̕��̊O���×{�ɂ�����N�Ԃ̍��z�×{��i�O���N�ԍ��Z�j |
 |
�@70�Έȏ�̔�ی��ҁE��}�{�҂�1�N�ԁi�O�N8��1���`7��31���j�̊O���×{�ɂ����鎩�ȕ��S�z���v��144,000�~�����ꍇ�A���̒������z�����z�×{��Ƃ��Ďx������܂��B
������i7��31���A��ی��Ҏ��S�̏ꍇ�͎��S���̑O���j���_�ŁA�����敪�u��ʁv�܂��́u�Ꮚ���v�ɊY����������ΏۂɂȂ�܂��B
���u������ݏ����ҁv�敪�ł��������Ԃ̎��ȕ��S�z�͌v�Z�Ɋ܂܂�܂���B
|
�� ���z��썇�Z�×{��̎x�� |
 |
|
 |
|
 |
